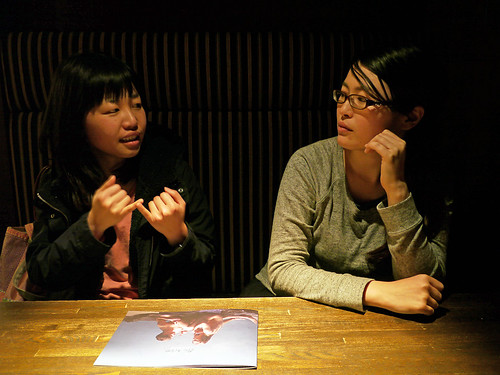![]()
映画『FAKE』森達也監督(右)、橋本佳子プロデューサー(左)
森達也監督がゴーストライター騒動で話題となった佐村河内守を追うドキュメンタリー映画『FAKE』が6月4日(土)より公開。webDICEでは、無音の"音楽"映画『LISTEN リッスン』の牧原依里・雫境(DAKEI)両監督による対談に続き、森達也監督と橋本佳子プロデューサーへのインタビューを掲載する。
webDICE編集部は、今回の両氏への取材の前に、配給会社の東風に佐村河内氏へのインタビュー取材を申し込んでいたが、「本作での佐村河内さんの稼働はございません」、そして佐村河内氏が完成したこの作品を観ているかどうかについても「佐村河内さんが本作をご覧になったかこちらで把握しておりません」という回答だった。
編集部はその後、佐村河内守氏と新垣隆氏それぞれに独自にインタビュー取材について問い合わせた。佐村河内氏の代理人である秋山亘弁護士は「メールは本人に転送しているが、基本的に取材は全て断っているので、難しいと思う」という回答、新垣氏のマネージャーは「まだ本人が作品を観ていないので、作品についてのインタビューに答えられない」という回答だった。
佐村河内さんにインタビューするメディアには協力できない(森)
森達也(以下、森):今回あまり取材は受けていないんです。なぜなら「この映画のテーマはなんですか」とか、「今、佐村河内さんに対してのほんとうの思いはなんですか」とか、「ラストのあのカットの後に、何を言ったんですか」とか、そういう質問には答えたくない。でもそういう質問をしてくるメディアに答えなかったら、ふてくされてるように見えて逆効果だから、受けないほうがと思っていたんだけれど、浅井さんがインタビューしたいと言ってると聞いて、古い付き合いでもあるし、浅井さんなら鋭い質問をしてくるだろうし、しかも橋本との合同インタビューだというから、それは面白いとふたりで話をして、お受けしたんです。
でも今、僕はあきれています。ついさっき、佐村河内さんの代理人の弁護士から連絡がきて、浅井さんが佐村河内本人に取材したいと打診していると聞きました。理由は、森監督と橋本プロデューサーだけでなく、多角的にこの作品を検証したいと。そんなもの映画にとって何の意味もないし、さらになぜ、その動きをこちらに隠していたのか。とにかく僕はあきれた。映画を壊したいの。いずれ公開すれば、例えば週刊新潮や週刊文春などのメディアが、そういう取材をやるかもしれない。その覚悟はしているけれど、なぜ公開前のこの時期に、よりによって浅井さんがそんなことをするのか、その説明をしてください。
──僕も映画の配給会社をやっているので、映画を潰すつもりはまったくないし、映画を応援するためにwebDICEという小さいメディアをやっています。
森:例えば『ゆきゆきて、神軍』の公開前に奥崎謙三にインタビューしたら、原一男さんがそれを喜ぶかどうかを考えてください。とにかく不愉快です。
──監督がそう言うなら、考えます。
森:誤解してほしくないけれど、最終的には取材申請して、取材をするかどうかは、そちらの自由です。
橋本佳子(以下、橋本):浅井さんの取材を受けるかどうかは、佐村河内さんたちの判断なので、私たちがとやかく言うことではないと思っているんです。
森:でも、そういう取材をされるんであれば、今日のインタビューは受けません。
橋本:佐村河内さんとは、私たちが「映画の宣伝だから出てください」と、お願いをする関係ではありません。
森:浅井さんは分かるでしょ?ドキュメンタリーは作為なんだから、その作為の裏を検証や解明などしてほしくない。しかも公開前に。
映画『FAKE』森達也監督
──今日のインタビューは、前半は、森さんがトライしたけれど完成しなかった作品も含めて、『A2』以降の15年間の森さんの活動について、後半は『FAKE』について聞きたかった。もちろん「最後の12分については言わないでください」と試写状にも書いてあるし、誓約書を書いているわけではないけれど、僕も映画の配給宣伝をやっているので、マナーとして最後をバラすつもりはまったくないです。
『FAKE』は、観る側が試されているな、と感じました。僕の立場は、映画のプロデューサーであり、配給会社も劇場もやっているだけれど、今日は、webDICEというメディアの編集者として来ました。森さんが何かの本に書いていたように、ジャーナリストは一線を越えることができる。ならば僕は編集者という立場で森さんや佐村河内さんに取材申請を出すことができるので、それを受けるかどうかは相手次第です。
配給会社の東風によると、佐村河内さんは映画を観たか観てないかも分かりません、という話だったので、音が聞こえないということであれば、字幕が入っていないと彼は手話通訳を介さない限り分からないと思ったのです。日本語字幕版が完成したら、僕らは別に、聾者の牧原さんと雫境さんが監督した『LISTEN リッスン』という映画を上映するので、スキャンダルな作品としてではなく、音楽家の映画だからふたりに日本語字幕入の本編が完成したら観てもらってレビューを書いてもらいたいと思っています(「佐村河内騒動描く森達也監督『FAKE』、無音の"音楽"映画『LISTEN リッスン』の聾監督はこう観た」)。
察するに、佐村河内さんは日本語字幕入りの本編ができていないのだから、作品を観ていないのだろうなと。ただ、森さんが仕掛けてきたものを、うぶに「そうですか」と受け取るわけにもいかない。だって「ドキュメンタリーは嘘をつく」と宣言している監督の作品をそのまま観るほど、森さんの作品を観て本を読んできた僕らはうぶじゃない。であるならば、編集者のポジションとして、佐村河内さんに意見を聞くのもありかと思ったんです。
森:途中までは分かるけれど、であれば、一線を越えて佐村河内さんにインタビューする浅井さんに対して、僕は不快です。やるのは自由です。勝手にどうぞ取材を申請して交渉を進めてください。ただし僕はあなたの取材を受けません。
──佐村河内さんをインタビューするメディアには協力できない、ということですね。
森:できないです。
──新垣さんは?
森:新垣さんはどうでもいいです。
──「ドキュメンタリーは嘘をつく」と森さんは宣言されているのですから、観客だけの一方向の視点だけではなく捉えたかった。別に真実探しをするつもりはまったくないですよ。
橋本:多角的に、というのは、具体的にどういうことですか?佐村河内さんや新垣さんに取材をして、いろんな角度からこの作品を取り上げるということですよね。私と森さんは制作者、被写体になっている佐村河内さん、サブで被写体となっている他の出演者の方々という意味で多角的に、ということですか?
──そこまでたくさんでなくても、映画の核になっている佐村河内さんと新垣さんに話を聞こうと思いました。
橋本:新垣さんは試写会には来ていません。映画を観てません。
──新垣さんの事務所とは連絡をとっていて、事務所の方は、本人はご覧になっていないと言っていました。
橋本:新垣さんのお兄さまと、事務所の方は来ています。
──だから、『ゆきゆきて、神軍』の場合は特別だけれど、アップリンクもドキュメンタリーを配給していて、監督と被写体だったら、被写体はプロモーションに出てきたりすることは多いです。でも、この映画はそうした作りになっていないことは百も承知です。であるならば、森さんの意見を、事の核心を聞き出すということではなくても、それを聞いて載せるのは、亡くなっている人ではなく生きている人だったら、メディアとしたら両者の意見を並列に表記するのは、そんなに不思議なことではないと思います。
森:だから、ワイドショーとか雑誌メディアなどがいずれやるだろうと僕は思ってるよ。なんで浅井さんがそれをやるの?メディアとしたら、と浅井さんは今言ったけれど、何十年も映画と共に生きてきたあなたなのに、なぜそんなことがわからないの? 充分に鋭い質問できるはずだよ。それをやらずして、佐村河内さんや新垣さんに裏を聞きにゆくと言うのであれば、なんでそんなに安易なんだとあきれます。
──森さんのインタビューをしたうえで聞きに行くというのは安易でしょうか?森さんが不快だとおっしゃったので、インタビューをやる、とゴリ押しをしているわけではありません。
森:だったら受けないですよ。浅井さんは何をしたいの?少し極端に言えば、公開前の手品を取材して、「こんなトリックがありました」と裏を暴いてどうするの?念を押すけれど、映画は手品とはぜんぜん違うし、トリックの意味も違う。例えば僕は、編集で落とした映像を公開することは絶対にしない。ありえない。時おりそういう人がいるけれど信じられない。それは映画の作為、仕掛け、トリックを暴いてしまうから。極端な話だけれど、それに近いよ。
──トリックがあるかどうかさえ僕らは分からないですよ。
森:当たり前です。編集におけるモンタージュやインサートもトリックです。勘違いしないでほしいのだけど、そのレベルでトリックと言っているのだからね。それをこの場で丁々発止浅井さんが聞いてきて、こちらもときにはのらりくらりしたり考え込んだり、今日はそんな取材ができるのかなと思って、来たんです。
──確信犯的に森さんはやっているに決まっているから、トリックはあるでしょう。
森:人の話を聞いてください。モンタージュやインサートや時系列の入れ替えなどは当たり前だと言っています。その集積が映画です。でも佐村河内さんに話を聞く、ということは、その裏事情を質問することでもある。ならば今の時点でその行為は作品を壊します。もう一度言うけれど、いずれメディアはそれをやりますよ。それを止める権限はこちらにないし、佐村河内さんが取材を受けるなら別にどうぞ、という話になるけれど、僕がいちばん腹が立つのは、なぜ浅井さんがそれを、しかも公開前のこの時点でやるのかです。まったく理解できない。映画に関わる人の行為とは思えない。
──要するにこの映画は、様々な社会問題がこれだけあるなかで、別に佐村河内さんの耳が聞こえようが聞こえまいが、あるいは、彼が作曲する能力があろうがなかろうが、僕らの生活に何の関係もない話で、もっと大事なことは、社会にたくさんあると思う。でも森さんがそれを撮るということは、この作品は、そんな佐村河内さん本人の問題より、観る側のリテラシーに問いかけていると思った。僕が一観客ならば混乱して、観終わった人と「あれってどうだったの?」という話をすると思います。ただ、さっき言ったように、腕章しているわけではないけれど、小さいメディアだけどメディアを名乗れば、取材申請もできるし、掲載することもできるんだったら、種明かしをしたいのではなく、映画について自分の疑問を聞きたい。佐村河内さんに会って「ほんとうは耳は聞こえるんですか」といった愚問ではなく、この映画を作っていくプロセスについて聞くのは、そんなに、週刊文春的ですか?
森:まったく同じです。一観客じゃない、と言ったけれど、一観客だったらこんな設定できないでしょう。だからこの段階で一観客ではない。
──そうです、映画メディアが当事者に話を聞くのはありではないですか。
森:ありじゃない。それだったら僕は闘います。映画を壊す行為だもの。もちろん、どんな話を佐村河内さんとするかどうかはまだ分からないですよ。接触して、それがパブリックになる段階で、僕にとってネガティブになります。というか、浅井さん分からないかな。映画という作品があって、被写体がそこにいて、それを僕は出したんです。本音を言えば、被写体について作品以外の部分を一切出したくない。
──でも彼も生きているし、生活している。
森:もちろん、だからそれは彼の自由だし、浅井さんの自由です。であれば、僕はこれには協力しません、ということです。
──要するに、この映画に関して、配給・製作サイドからは一切、彼のコメントは出てこないということですね。普通、生きている被写体であれば、何らかのコメントなりは出すじゃないですか。出さない場合もあるんだろうけれど。
森:配給・製作サイドからは、映画で全て語っているから。僕だってインタビューもあまり答えたくないんです。それは浅井さん、分かるよね。映画を撮って、映画がそこにあるなら、あとはそっちで勝手に解釈してくれればいい、と本当は言いたいけれど、そんなこと言ってたらパブリシティが出ないから、渋々やってるわけですよ。でも浅井さんだというから、ぜったい面白い取材になるね、ということで来たんです。でもそれが、来る直前に佐村河内にインタビューを依頼している、というのが分かって、なんだよそれはって。
──橋本さんはどう思うんですか?誤解しないでほしいのは、ゴリ押ししたいのではなく、考え方を理解したいだけなので。
橋本:このやりとりだけでも充分面白い記事になりますね(笑)。というのは置いておいて、事実だけ言います。佐村河内さんのメディアへの取材依頼は、担当の秋山弁護士さんを通じるんです。公開が決まってからは映画に関する取材もあるので、私たちにも「映画についてこういう取材依頼があります」と一報をくれるので、それで浅井さんの佐村河内さんへの依頼を知ったのです。同時に、佐村河内さんご自身からも「秋山さん経由でアップリンクの取材依頼が来たけれど」と連絡が来たので、森さんと共有しました。取材依頼書に「多角的」とあったので、多角的というのは佐村河内さんだけではないかも、という話をして、とにかく浅井さんに聞いてみようと。森さんの話に製作者の私が補足するインタビューで記事が出る場合と、そうではなくて、その記事全体が多角的に作られる場合とでは、取材を受ける側としての考え方が違うと思うんです。
──橋本さんは製作者として、佐村河内さんに僕がインタビューをするということは反対ですか?
橋本:この作品にトータルに関わってきた者としては、一概に反対ではないです。
──おふたりは意見が違うということですか。
橋本:ただ、佐村河内さんがどのようにメディアに登場されるかに関しては、インタビューに出ることが反対とかwebDICEに出ることがどうなのか、ということではなく、私はものすごく関心を持っています。なぜかというと、佐村河内さんはずっとメディアのインタビューを受けていないんです。インタビューを受けたのは、映画に出てくるフジテレビの報道番組の1年ちょっと前に出たインタビューと、デビッド・ディヒーリたちが取材をしていた海外の雑誌「NEW REPUBLIC」、そしてビッグコミックスペリオールで連載中の吉本浩二さんのルポマンガ「淋しいのはアンタだけじゃない」の3つだけです。
佐村河内さんと私たちは、利害関係が一致しているわけでもないです。ただ、佐村河内さんがどういうメディアに次に出て、どういう発言をするかは、映画で関わった者としてはたいへんな関心を持っています。
浅井さんが今インタビューをお申し込みになっているこのことに、佐村河内さんが出たほうがいいか、出ないほうがいいか、ということに関しては答えを留保します。
橋本佳子プロデューサー
この映画をどう検証してもいい、
そのことで映画が壊れるとは思っていない(橋本)
──配給会社はどう考えているのですか?
木下繁貴(配給会社東風代表 以下、木下):スタッフの酒井からメールで回答させていただいているように、この映画に関しては佐村河内さんにパブリシティへの取材協力はお願いしていないし、協力していただく予定はございません。
橋本:ですから直接、取材依頼をしたんですよね。私は佐村河内さんがいろんなインタビューを受ける・受けないに対して製作サイド側が注文つけられる筋合いでもないし、佐村河内さんが出たいというものに対して出て欲しくないというのも、出たくないものに対して出てほしいという立場でもない。ただ、どういう風に出るかに関しては、とても関心を持っています。
先ほどまで、佐村河内さんがwebDICEに出るということを知らなかったので、それについては、どういう風にジャッジをしたらいいかは吟味する時間がないです。
──わかりました。森さん、僕の基準はぜんぜん別なところにあって、森さんとの友情というか、同じ土俵でやってきた同士だと思っているので、であれば、そっちをとるしかないですよ。メディアの論理といったことは別にして、森さんがイヤだと言うならそうします。
橋本:私も昨日から、森さんと浅井さんの深い話をすごく楽しみしていました。
──僕も同じです。
橋本:それなのに、つい1、2時間前に秋山弁護士から連絡があったので「なんなの、それ」という話になったという状況です。
──率直に言えば、森さんに騙されたくないなと思ったんです。この映画を観て、メディアの特権としてインタビューを申し込んで、観客にできないところをやらせてもらえるということだったので。映画を観ているだけだと、答えは当然出ないままで、森さんの術中にはまったままで、ちゅうぶらりんでこの映画を観た人と話すしかない。でも森さんと話す機会を与えられても、マナーとして、「実はあれはどうだったんですか」と聞くことは、インタビューする側としてもかっこわるい。でも、そうすると、いい意味で騙されたまま記事を書かなければならないな、と思ったんです。そこが若干、自分としては正直に言えば癪だなと予想できた。なので、事実の補強ではないけれど、他の人の観方はどうなのか、というところを聞いてみたいと思ったんです。それは、数人のライターと座談会形式で観方の違いを語ることもできるだろうけれど、もうちょっと、自分たちのメディアとして取材申請できないことはないので、だったらやってみようと思ったんです。好奇心です。
森:だから、僕はそれを止める権限もないし、どうぞやってください、ですよ。ただならば、これは受けないです。浅井さんは「騙されっぱなしでいいのか」と言ったけれど、それはこっちはそうしたいよ。
──(笑)。
森:騙すって言葉が適当かどうかは別にしても、実はそんなにこの映画は、そのレベルで嘘をついていないよ。どうも過剰に考えすぎている。けれど、悔しいという気持ちも分かるけれど、じゃあ悔しかったら、はい、これがトリックですよ、と出したくないというのは分かるでしょう。だったら「他の人に話を聞いてくるよ」と言われて、「ちょっと待ってくれよ」とこちらが言うのは当たり前じゃないですか。とてもシンプルですよ。だから、やりたいならどうぞ。たぶん浅井さんがやらなくても、きっとどこかがそのうちやるでしょう。特に公開が始まれば。
──やるでしょうね。
森:新垣さんのインタビューが出るかもしれないし、神山典士さんのインタビューが出るかもしれない、それはいいよ。ただ、もう一回言うけど、なんで浅井が?って僕はさっき思ったよ。なんで映画壊すの?って思った。
橋本:あの、ちょっと違うと思います。別にいろんなところが検証してもよくて、あまりそのことで映画が壊れるとは思っていないので、怖くないです。そんなことではこの映画は壊れないと思っています。でもだからといって、どうぞ取材にじゃんじゃん行ってください、というのではないですけど。
森:だから今言ったように、そのレベルの嘘などついてない。別に恐れていない。ただ一言にすれば、とても不愉快です。『A』のときも、荒木さんとふたりでインタビューを受けてほしいと言ってきたメディアが複数あって、あきれながら断ったけれど、浅井さんはその気持ちはわかるよね? 理屈じゃないです。気分の問題です。それはやっぱり、今日の取材を楽しみにしていただけに。
──僕も取材する立場で、楽しみにしていましたから。じゃあ、佐村河内さんには取材しない、ということで、インタビューをはじめていいですか。
森:だったら受けます。
【森さんは一時退席】
──webDICE以外にも、佐村河内さんにはたくさん取材依頼は来ているんですね。
橋本:そこは配給の木下さんにお願いしています。でも佐村河内さんは基本的に受けないので。あれから2年経って、先ほど言った3件しか受けていないです。自分がそんなにしゃしゃり出て、いろんなところで自分のことを主張する立場でもないと、言ってました。
ある人物ドキュメンタリーを撮ったとき、その被写体の人と監督とが一緒にキャンペーンしたりというのは『ニッポンの嘘 報道写真家 福島菊次郎』のときもそうだったし、よくあることなので、浅井さんが、今回、特殊なことをされているとは、私は思っていないです。
──佐村河内さんは、この映画についてハッピーなんですか?
木下:どういう風に見えましたか?
──分からないです。
橋本:この質問には、私ではなく監督が答えるほうがいいと思います。
【森さん戻ってくる】
──では佐村河内さんにインタビューしないということを約束します。今までのやりとりは掲載してもいいのですか?オフレコですか?
森:ほんとうにしつこいやつだなぁ(笑)。
──僕もお金と時間をかけた作品を潰すつもりはまったくないし、配給会社の社長として分かるし、応援するつもりでwebDICEは作っているし、監督にインタビューするときにも、自分が面白いと思った監督にインタビューしに行っているので。ただ、今回は初めてのケースなので。
森:単に「不快だ、と森が言った」というのでとどめてくれるならOKです。
橋本:さっきのことがもう一回聞きたかったら、今から仕切り直して、もう一度聞いたらどうですか。その方が後でもめないと思います。
森:騙す・騙されるという言葉が一人歩きしてしまうのが怖いから、そのへんはなしにして、「被写体にインタビューされることを森は頑強に否定した」で、それは出してくれてもいいですよ。……出したいなら。あんまり出してほしくないけど。
──分かりました。では、始めます。
オウム事件以降、日本は“集団化”への道を辿った(森)
──試写状にも森監督の熱いメッセージが入っていて、試写状にこういうメッセージがあるのは珍しいですよね。
多くの人にご無沙汰しております。森達也です。
肩書の一つは映画監督だけど、4人の監督の共作である『311』を別にすれば、本作『FAKE』は15年ぶりの新作ということになります。「下山事件」に「中森明菜」、「今上天皇」に「東京電力」など、撮りかけたことは何度かあったけれど、結局は持続できなかった。
でも今年、やっと形にすることができました。映画で大切なことは普遍性。入口はゴーストライター騒動だけど、出口はきっと違います。誰が佐村河内守を造形したのか。誰が嘘をついているのか。真実とは何か。虚偽とは何か。そもそも映画(森達也)は信じられるのか……。
視点や解釈は無数です。絶対に一つではない。僕の視点と解釈は存在するけれど、結局は観たあなたのものです。でもひとつだけ思ってほしい。様々な解釈と視点があるからこそ、この世界は自由で豊かで素晴らしいのだと。
僕がドキュメンタリーを撮る理由は何か。もちろん一つではないけれど、最終的には「見て見て!こんなのできたよ!」です。すべての人に「見て見て!」とお願いしたい作品になりました。
(以上、『FAKE』試写状より引用)
森:蛇足ですよね。僕もそう言ったんだけれど、配給からぜったい入れろと言われて。
──それは充分伝わりました。15年ぶりの作品ということで、オウム事件から今年で21年。20年のときに森さんはイギリスにシンポジウムのために行かれて、オウム事件からの20年で日本がいちばん大きく変わったかについて、どう答えられたのですか?海外の人は、どういう風に日本が大きく変わったと分析しているのでしょうか?
森:イギリスではオックスフォードやマンチェスターにエジンバラなどいくつかの大学で、『A』の上映と、その後のシンポジウムに参加しました。そもそも、なぜオウム事件から20年のシンポジウムがイギリスで行われたのか、というと、やっぱりISの存在です。ISはアラブ圏以外の国からも多くの人が参加しているけれど、イギリスは最も多いんです。つまりテロの被害国であると同時に加害国でもある。でも被害意識ばかりが突出して、大きく国の形が変わろうとしている。この局面をどう考えるか、というときに、20年前の地下鉄サリン事件とその後の日本社会の変化は非常に大きなキーワードであると、そういう認識をイギリスの研究者は持っています。
言い換えれば、オウム以降、日本社会がどのように変質したかを検証しようということなんです。そこには、日本社会が悪くなってしまったという前提がある。日本からの留学生とも話したけれど、10人いれば9人が、「今の日本には帰りたくない」と口にします。
──悪くなったというのは、どういう意味でですか?
森:彼らはネットで日本の情報をチェックします。自己責任とか非国民とか、そんな記述を目にするたびに絶望的な気分になる。それはよくわかります。多くの日本人はもう馴れきってしまっているけれど、視点を変えればありえないほどに不寛容な社会になっている。
こうした現象がなぜなぜ始まったのか。その起因を言葉にすると、集団化です。地下鉄サリン事件によって不安と恐怖を刺激されて、人というのは怖くなると集団になりたがりますから。みんなで連帯したいといった気持ちが生まれてくる。911の後のアメリカが端的な例です。まずは愛国者法を制定して、集団内の異物を排除しようとする。次に集団は敵を探します。なぜなら共通の敵を発見すれば、さらに一丸となれるから。こうしてアメリカはアフガニスタンとイラクに侵攻して、イラクに至っては大量破壊兵器が自分たちを脅かそうとしているなどと大義まで捏造して、フセイン体制を崩壊させた。その帰結としてISが生まれている。全て連鎖しているわけですが、実はその6年前に日本でも、オウムによってその集団化が起きていた。サリン事件以降、例えば街には監視カメラがどんどん増えたり、街の自警団も急激に増殖した。要するにセキュリティ意識が肥大するわけです。集団は同じ行動を強制します。つまり同調圧力もどんどん強くなる。違う動きをする者は異物として、不謹慎などの理由をつけながら攻撃したくなる。
さらに集団は、同じ動きをするために、強い言葉を発する政治家、リーダーがほしくなる。それもアメリカを考えれば分かりますね。ブッシュ政権の支持率は、911後に急上昇した。サリン事件が起きた95年は自社さ政権でした。だから自民党への期待が高まった。東日本大震災のときは民主党政権です。社会全般が集団化するとき、リベラルな政権では生ぬるいわけです。もっとマッチョな政治家を求め始める。今のアメリカやヨーロッパだけではなく、歴史的にも頻繁に表れる現象です。
──ナオミ・クラインがショック・ドクトリン(大惨事につけこんで実施される過激な市場原理主義改革)をテーマでドキュメンタリー映画にしていましたが、日本にショック・ドクトリンをしやすい状況ができているということですね。
森:まさしくそうですね。
この20年でテレビは少しずつ衰退の時期にきている(橋本)
──橋本さんは、テレビがメインの仕事で、この20年間は、日本のテレビのメディアに絞って、大きな変化は感じましたか?
橋本:感じました。どのメディアにもピークがありますが、日本映画のピークは50年代で、テレビの出現で斜陽になったというのは、さておき、この20年はわりとテレビメディアの力そのものが下っていった時期だと思っています。影響力もそうだし、テレビから生まれるものも含めて、少しずつ衰退の時期にきているのかなと感じています。私たちは今、ピークを過ぎたそのなかにいるのだと。それは衰退していくこと自体をネガティブには捉えていないんですけれど。
──「良質な情報」は衰退していくけれど、集団化している状況であるならば、テレビというメディアを使った「洗脳」はよりしやすくなっているのではないですか。
橋本:そうした抽象的なことではなくて、完全にテレビを観る人口が少なくなっている。セット・イン・ユース(ある特定の日の特定の時刻にスイッチが入っている受信機の台数)も下がっているし、それから媒体価値も下がっている、そういう意味での影響力の低下です。それが人にどう影響を及ぼしているか、はもちろんあります。「良質」か「良質でない」かということはなかなか一概には言えないと思っていますから。
──それは、インターネットも含めたメディアとしての接触率が下がっているということですか?
橋本:媒体の力ですね。テレビそのものを観る人口が減っているし、20年前まではテレビを観たことがないとか、観ない、という人が実はあまりいなかった。でも今は、家でもテレビを片付けている人とか、テレビではない情報をインターネットで取ろうとしている人が増えて、じゃあ今のテレビに何を求めているのかは、この20年でいろいろ変わってきていると思います。
でも、浅井さんがおっしゃるように、テレビそのものが同調圧力を強めているか、というと、もともとテレビって媒体としてそういう力は、内在的に持っているんです。
──森さんは、今の橋本さんの意見に同意ですか?
森:内在的に持っている、というのはまったくその通りです。要するに商売ですから。テレビや新聞、出版社、アップリンクにしたって、どうやったら観てもらえるか、どうやったら読んでもらえるかを第一義に考えるわけですよね。この20年、という言い方をすると、95年は阪神淡路大震災に、サリン事件だけじゃなくて、WINDOWS 95が誕生した年でもある。まさしくネット元年。ということは、ネットが勢力を拡大することで、既成のメディアが危機感を持った。それによって、市場原理がより強くなった。競争原理が激しくなって、結果として非常に刺激的で刹那的な情報に傾斜するようになった。さらに社会全体が不安と恐怖を持ってしまっている。こういうときに危機を煽れば、より多くの人がチャンネルを合わせてくれる。あるいは、キオスクで新聞を買ってくれる。その傾向は、例えばアジア太平洋戦争が起きる前の新聞などを例に挙げるまでもなく、以前から存在しています。内在的にメディアはそうした市場原理を持っているけれど、それがより一層に露骨になったのがこの20年だと思います。
──そういう意味では強くなった、とも言える?
森:僕はそう思っています。非常に激しくなったと。
──下山事件や東京電力、中森明菜といったいくつかの中止になった企画が試写状にも書いているけれど、今上天皇は、フジテレビの「NONFIX」でやろうとした企画で、テレビ局の圧力で中止になったのですか?
森:圧力というと少しニュアンスが違う。このときの企画は、僕が天皇に会うまでの過程を、これに対しての周囲の反応を主軸にしながらドキュメントにすることでした。最後に会って「お辛いですか?」と聞く、という企画だったので、フジテレビの編成から、「天皇に会えるはずがないので、この企画は難しい」と言われた。これに対して、「会う、会わないは実のところどうでもよくて、会えなかったら会えないなりの結末をちゃんと考えてますよ」と言ったんだけれど、「会えないから駄目です」の一点張りだった。僕も馬鹿じゃないから分かるけど、それは彼らのエクスキューズなわけで、本音はとにかく何でもいから天皇はやめてくれ、ということですね。そのときの番組枠である「NONFIX」では、シリーズとして憲法がテーマでした。他に是枝裕和さんや長嶋甲兵(TV番組制作会社テレコムスタッフ所属のプロデューサー)さんなどがいて……。
──森さんは1条をやったんですね。
橋本:是枝さんが9条をやって、ドキュメンタリージャパンの長谷川三郎(映画『ニッポンの嘘 報道写真家 福島菊次郎』監督)は24条の男女平等をやって。
森:長嶋甲兵さんは96条の改正かな。
橋本:そうした5、6本のシリーズを別々に制作やっていたので、森さんの1条がなぜ無くなったのかは詳しくは分かってなかった。
──森さんは結局、降りたのですか?
森:降りたというか、これ以上無理だなと。天皇に会うまでの過程がドキュメンタリーの主軸です。だからフジテレビとの話し合いの際にも、了解をもらってカメラを回しました。もしも奇跡的に継続できるなら、ここも重要な要素になると思って。でも何度か議論したけれど、最後にはあきらめた。放送権を持つのは彼らですから。その後に、映画でやればいいじゃないか、という話も来たけれど、映画じゃ意味がないんですよ。テレビというマスメディアのなかで、天皇を撮るということの摩擦をテーマにしたかった。でも、摩擦どころじゃなかったというのが僕の読みの甘さですね。
──今いみじくもおっしゃったように、テレビの力を森さんは認めているのですね。
森:テレビは大事なメディアです。決してテレビを軽視していないし、軽蔑もしていないです。
橋本:私は、テレビで育って、番組制作を仕事にして、まさにテレビ人間だと思っています。今、テレビの力が落ちてきているというのは、中にいる自分が一番感じているのですけれど、それは自分たちに責任がある、ということも含めてです。
テレビと映画の壁を壊すことに、今後の日本のドキュメンタリーの可能性がある(橋本)
──ドキュメンタリージャパンとしては、テレビの番組制作から映画にシフトしているのですか?経済的にドキュメンタリー映画が社員を支えるほど利益を上げているわけではないというのは分かりますが。
橋本:切り替えてないです。最近、映画を何本も作っているけれど、結局、すべて私のプロデュースです。会社の中で、ひとりでシコシコ映画してます。でも、私も、5月はテレビ・ドキュメンタリーの放送をし、6月に『FAKE』を公開して、7月に『いしぶみ』(是枝裕和監督)を公開して、8月はドキュメンタリー・ドラマを放送、と映画とテレビが半々くらいになっています。
──でも、森さんはテレビで摩擦を起こそうと思ったけれど、できなかった。橋本さんはいかがですか。
橋本:摩擦は、起こそうと思わなくても起きることはあります。私はスタッフではないですが、ドキュメンタリージャパンでも私が代表の時、10年間裁判をやりました。NHK ETVの従軍慰安婦の番組です(「女性国際戦犯法廷」番組関連訴訟)。最高裁まで行きました(2008年6月、NHK・NHKエンタープライズ21・ドキュメンタリージャパンの三者を訴えていたVAWW-NETジャパン[「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク]側が敗訴した)。もちろん、私自身は摩擦を起こすためにテレビを作ってはいないです。森さんはそうじゃないと思うんだけど。
森:僕も別に摩擦が目的じゃないです。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
──では、映画のほうがテレビのドキュメンタリーよりも表現としては自由だと思われますか?
橋本:あまりそうは考えていないですし、そもそも、テレビも映画も、映像コンテンツとしては、いずれ境がなくなると思っているので。
──アメリカのHBOやフランスとドイツのARTE(アルテ)といったテレビ局が作ったドキュメンタリーをアップリンクでは映画として劇場で配給しています。
橋本:日本のテレビドラマと劇映画の関係は、昔からあり、テレビと映画の作り手同士も、行き来しているじゃないですか。でもテレビ・ドキュメンタリーというのは、なぜかテレビはテレビ屋さん、ドキュメンタリー作っているのは自主映画の人、と今までは間違いなく高い壁があったんです。この10年ほどで、東海テレビが映画の上映もしたり、作り手同士が交流したり、壁が崩れ始めた。そもそも、テレビと映画は明らかに違います。作り方も違うと思っています。でも、ドキュメンタリーは、両者とも閉塞状況にあり、ドキュメンタリー映画は儲からない、と浅井さんが、先ほどおっしゃっているように、自主映画は苦しいし、じゃ、テレビのドキュメンタリーに場があるか、といったら少ない。
──放送する枠がないということですか。
橋本:ドキュメンタリーの放送枠が少ないですよね。ということは、作り手が自由になりづらい。不自由なところからは、面白いものは生まれてこない。それだったら、テレビと映画の垣根を越える試みが、そういう状況に風穴をあけられるのではと思ってます。例えば海外でドキュメンタリーを製作する場合は、劇場版のバージョンと50分のテレビ版と必ずセットの契約になっています。その分の収入も見込めるということ含め、日本のテレビ局でも考えるべきだと。
テレビってやっぱりある程度のお金があるので、そこは境目を越境していく。作り方もテレビ的な手法で作ったもの、映画的なものと、お互いに切磋琢磨でき、新たな方法論がうまれる可能性がある。NHKでも、最近の企画募集で、ノーナレーション、海外でも通用し、映画にもなるドキュメンタリーというものがあり、なるほどと思いました。
だから、テレビも変わろうとしている。それはひとつには、国内的な事情もあるけれど、グローバルなテレビ市場を見たときに、日本のテレビ・ドキュメンタリーは海外作品と戦えていない。テレビと映画の壁を壊すことに、今後の日本のドキュメンタリーの可能性があると思います。
──スポンサーによって成り立っている民法のテレビよりも、HBOとかNetflixといったサブスクライブ形式のテレビの方が、テレビドラマにしてもドキュメンタリーに関してもより規制が少ないように思うのですが、日本ではそうした取り組みは考えられているのですか?
橋本:私もいくつかのドキュメンタリーに関しては、ネットメディアと組んでということを考えてトライしましたし、これからもするだろうと思います。現在は、2017年の公開予定の作品で、それが成功しているので、進めています。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
佐村河内さんに会って、これは画になるなと直感で感じた(森)
──今回の『FAKE』の企画は、森さんが持ち込んだのですか?
橋本:路上を歩いているときに、「撮りたい人ができたんだけど」と森さんから電話がかかってきたんです。
森:実はその前に、東電のドキュメンタリーを一緒にやろうと思っていたんだけれど、僕がやる気なくして途中で止めてしまって……。
──東電は橋本さんの企画だったのですか?
森:僕です。他愛のない話だけれど、東電が何百時間も事故の渦中の映像を発表したじゃないですか。
橋本:あれで『アトミック・カフェ』みたいなのができないか、と話をしていたんです。
森:これをギャグにしてしまおう、と思いついて、ハードディスク買ってもらっていろいろ調べていたんだけれど……。
橋本:そのうち白石(草/OurPlanet-TV)さんが『東電TV会議 49時間の記録』としてちゃんとやりだしてしまったし。
森:自分から言い出しておきながら止めてしまって申し訳ないなと思っていたので、佐村河内さんに会ってその後に、橋本さんどうかな、と電話をかけたんです。
──佐村河内さんを撮る、ということを聞いたときは、どう思われましたか?
橋本:週刊文春の読者なので、どんな人かは知っていて、あとワイドショーやNHKスペシャルを観たくらいかな。あまり関心なかった。だけど、佐村河内さんに会いに行ったら、その瞬間に、森さんが撮りたいという気持ちがすぐ分かったんです。私も福島菊次郎さんに会ったときそうでしたが、「この人撮りたい!」って人がいるんですよ。理屈ではなく、長い間ドキュメンタリーをやっていると、意味もなく、その結果がどうなるか分からないけれど撮りたい、と思うことがあるんです。
──森さんは週刊文春の記事を読んだ程度の知識だったのですか?
森:僕も騒動になる前は知らなかったし、NHKスペシャルも観ていなかった。騒動が起きて初めて、「へぇ、こんな人がいたんだ」みたいな程度でした。
──著作のなかで「ねぇねぇ、こんなこと知ってる?」という気持ちが森さんの映画を撮るきっかけだと書かれていましたけれど、撮り終わってからであれば佐村河内さんのことは観客より知ってると思うけれど、撮る前の段階では、どこが森さんのアンテナに引っかかったのですか?
森:そもそもは編集者から、佐村河内守についての本を書かないかと依頼があったんです。その編集者は本人に何度も会っていて「相当今のメディアが伝えていることは違うことがたくさんあるんだ」と言うのだけど、ぜんぜん気乗りしなくて、一回断ったのかな。でも、何度も連絡してきてくれたので、じゃあ1回くらい話を聞いてみようかなというレベルで会って話をしたら、橋本さんと同じで「これは画になるな」と、別に理屈じゃなくて、直感で感じたんです。
──そのときはカメラは?
森:もちろん持っていってないです。その場で2時間くらい話をして。隣に奥さんの香さんが座って手話で通訳をしてもらいながら、でした。話がほぼ終わって「あなたを映画に撮っていいですか?」と言ったとき、隣に座っていた編集者は、きっと茫然としていたと思う。申し訳ないことをしちゃった。
橋本:たぶんその後、すぐ私に電話をしたんだと思います。
森:その場では、彼はすぐに回答はしなかった。ありえないという雰囲気でした。
──森さんはたくさんの本を出版されていて、本の方が読み手の思考回路にダイレクトに入ってくるじゃないですか。なぜあえて映画にしたんですか?
森:いみじくも浅井さんが言ったように、今回はダイレクトにしたくなかった。間接話法で行きたかったんです。そもそもこれまで15年撮らなかった理由は、ひとつは人をこれ以上傷つけたくなかったから。『A』『A2』でたっぷり傷つけたから、もうこれ以上人を傷つける仕事はしたくないと思った。けれど、結局は、その彼の魅力が勝ったということでもあるし、もうひとつは、その間ずっと本を書いていましたけれど、確かに本は文字ですからとても直接的な表現で伝えられるけれど、だから物足りないわけで。「世界を平和にしましょう」ってぜんぜん間違っていないけど、それを言葉で言ってしまったら単なるスローガンです。それを(目の前のカップを指して)このカップを撮りながら世界平和がいかに大事かを伝えられたら、これはものすごく届く。やっぱりそういう表現をしたいと思っている時期だったので、その場で、自分のなかで適合したという感じです。
被写体に寄り添ったら、ピントが合わなくなる(森)
──町山智浩さんはTBSラジオの「たまむすび」で、後半の展開には直接触れていないけれど「ラスト12分は、やらせですよ。森監督は、佐村河内さんにあることをやらせるんです」と言っているし、試写を観た何人かの人に感想を聞いたんですが、ある人は「森さんは食えないね、怖いね」と言っていました。今回の作品では、佐村河内さんは傷ついていない?
森:いや、傷ついているでしょう。
──そこが、監督の怖いところですかね。
森:うん。まぁ……映画の被写体で傷つかない人なんていないですからね。それはもちろん、テレビのドキュメンタリーでもそうだけど、1分間の村祭りの報道で20秒映ったとしても出た人は傷つくかもしれない。
橋本:それはドキュメンタリーの持つ宿命みたいなものかな。
森:出て良かったというところがあるかもしれないけれど、同時に傷つきもしてるでしょうし、それはそういうものだと思う。近頃は「被写体に寄り添う」というフレーズを使いたがる人がとても多いけれど、寄り添ったらピントが合わなくなります。僕の感覚では、とても不思議です。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
──ドキュメンタリーの製作費は、監督の生活費だ、と僕は映像制作ワークショップで言ってるんですけれど、今回ドキュメンタリージャパンが製作に入っていて、予算やスケジュールについては、橋本さんはプロデューサーとして最初にイメージされるのですか?
森:僕の条件は毎月ギャラ500万だから(笑)。
橋本:あのですね、浅井さんもプロなので、この映画がどれくらいの予算かは分かると思うんです。
──人件費はなかなか分からないです。
橋本:東風さんとDVD関連の2社に入っていただき、制作費は、最終的には何とかなりそうです。
木下:それから森さん自身も出資して、作品の権利を持っています。
橋本:森さんから最初にこの話を持ちかけられたときに私は「やりたいけれど、私お金ないからね」と言った覚えがあって。監督とふたりでいろんなところにお金を集めに行ったけど、うまくいかず……。
でも、ギアナ高地に行くわけではないし、近郊の撮影だし、制作会社として少しは基礎体力はあるので、それで始めたんです。ただ、先の見えない取材だったし、どこまで撮ればいいのか分からないし、途中で東風さんにお話したり、今組んでいる株式会社ディメンションと株式会社ピカンテサーカスという2社にお話したりしてなんとかなりました。
──その2社はどんな会社なんですか?
橋本: DVDを出している会社です。
──ではDVDはそこからリリースされるんですね。
木下:そうです。
橋本:原一男監督の作品をリリースしていて、今度小川プロの全作品をリリースするそうです。
森さんと一緒にお金集めにまわったところは、いろんな事情ですべてうまくいかず、断られてばかりで萎えました。それとテレビ局にはこの企画は無理だとわかっていたので、打診もしなかったし、ほそぼそと撮影していました。
──プロデューサーとして、自主映画みたいにお金だけ出して、何もリクープしないというのは会社が困りますよね。
橋本:私は、今は役員でもなんでもないので、リクープできなかったら、クビになるかもしれないです。
──その時点で、どういうところで売上を回収しようと思っていたのですか?
橋本:ドキュメンタリーって、劇場だけじゃなくて自主上映会の収入が馬鹿にできないですよね。でも、森さんに私は、「この作品は自主上映会は見込めないので、劇場で回収するしかないよね」ということを最初から言っていました。自主上映会向きではないと思ってました。
──森さんはそれはプレッシャーではありませんでしたか?
森:『A』や『A2』、『311』も自主上映会なんてしてもらえないし、はなから眼中になかったから。
橋本:私は、森さんと撮影を始めてちょっとしてから、『A』と『A2』の興行成績を知ったんです。それは結構ショックで。森達也さんだからきっと基礎票はいっぱい持ってるだろうと思ったら……うん、まあそうか、これだけなんだみたいな。
森:愕然としてたよね。「これしかいないのかよ」みたいな顔してた。でもその程度です。福田和也さんからは以前、「高名だけど誰も観ていない映画」と言われたけれど、実際にその通りだと思う。
──15年前といえば、今30歳の人はまだ15歳だった。
橋本:まあ、映画は長い目でみるしかないので。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
『FAKE』というタイトルには多義性がある(森)
──撮影で現場に行くのは、森さんと山崎裕(撮影監督)さんと橋本さんですか?
橋本:山崎さんが撮影のときは、もうひとり録音担当がいます。でも山崎さんは京都のシーンとか、それほどの日数は回してないですね。森さんひとりじゃ無理だろうという場面で撮ってもらいました。
森:そもそも、ドキュメンタリージャパンにお願いした理由は、今回は山崎さんのカメラでやりたい、ということもあったんです。『A』や『A2』は一部に安岡卓治のカメラがあるけれど、テレビの『放送禁止歌』なども含めて、ずっと僕はひとりで撮影してきたから、自分のカメラワークの限界も知っているし、ちゃんとしたカメラで映像を作りたいというのがあって、すべてのロケは無理ですけれど、ポイントで山崎さんにお願いしたいというのがあったんです。
──橋本さんも撮影で佐村河内さんのマンションには行かれているんですか?
橋本:行ってます。
──森監督に橋本さん、山崎さん、すごいメンバーですよね。佐村河内さんからしたら、あの部屋で圧迫感はなかったんですか。
森:うーんどうだろう、ドキュメンタリー映画にそんなに一般の人は関心がないし。僕の名前だって知らなくてもおかしくないし。
──いえ、3人いると人としての圧力があるなと。
森:それはあるかもね。酸欠になる。
──配給会社の東風はどこで入ってきたのですか?
橋本:制作の途中ですね。私がそろそろ考えないと辛いな、という時期にお願いしました。
──『FAKE』というタイトルは、どなたが決めたのですか?
橋本:最初は森さんですね。私はいつもテレビもそうなんですが、タイトルはプロが決めたほうがいいと思っています。宣伝配給の人の意見や、テレビだったらPRやっている方たちが字数まで考えているので、そうした人たちの意見をまず聞きます。そのときに横文字はよくないとか、そういう意見はいっぱいありました。
木下:配給会社としては最初反対しました。アルファベットの表記で分かりづらい、カタカタにしても間が抜けているし、違う映画を思い出してしまうし。
──森さんはなぜそれを思いついたのですか?
森:わりと最初から言っていたよね。
橋本:撮影をし始めて1ヵ月で仮タイトルとしてついていました。
森:このあいだ、誰かから「お前の映画のタイトルはアルファベットと数字しかない」と言われて、確かにそうだと気がついた。……たぶん、あまりタイトルに意味を込めたくないんです。でもタイトルなしというわけにはいかないし、本音はなんでもいい、なんですけれど。
──『FAKE』ってめちゃくちゃ意味がありますよね。
森:多義性がある。この『FAKE』は何を指しているのか、とか。特に映画を観終えた、エンドロールが上がる前であれば、この文字が上がることで、もう一回あらためて、いったい何がFAKEで何がFAKEじゃないのか、そもそも森はFAKEなのか、この映画はFAKEじゃないのか、といろんなことをみんなが煩悶すると思うので、そういう意味ではうってつけかなと。
──文春的に考えれば、『佐村河内さんの真実』というタイトルですよね。
森:うん、真実は排他的でしょ、でもFAKEはすべてひっくるめちゃう。だから「真実」という言葉はぜったい使いたくない。
──それでは『森達也の真実』でしょうか。
森:うーん、しいていえばそうなるけれど、それは『森達也の真実(FAKE)』としてもいいんじゃないですか。
──なるほどね。観客が実験台にされているような感じで。
森:(笑)。
──森さんは「ドキュメンタリーは嘘をつく」と宣言されているわけで、森さんの映画を観に行くひとはそこまでうぶじゃなくて、どう嘘をつくのか、と観に行くと思うんです。
森:「ドキュメンタリーは嘘をつく」という言葉が一人歩きしすぎちゃっているけれど、その嘘って、捏造したり、演技を指導したりということじゃないからね。表現というのはそもそもがすべからく嘘なんだよ、という意味での「嘘をつく」ですから。あの本はプロデューサーの土本典昭さんにも献呈したのですが、律儀な方なのですぐ御礼のはがきをいただいたんだけれど、「とてもいい本です、素晴らしいです、ただしタイトルがいけません。嘘ではないのです」と書いてあって、確かにそうだなと。だから正確には、「嘘」という言葉はたぶん不的確だと思います。「嘘」も「真実」も含めた曖昧な、そういった領域なので。ただあの本のタイトルは編集に押し切られて、まぁタイトルは扇情的でいいやと決まった。だから「嘘をつく」と僕はしょっちゅう言ってるように見られているけれど、それはみんなが言ってる「嘘」とはちょっと違うんだよ、ということは留保しておきたいです。
──世間で言う「やらせ」ではないということですね。
森:もちろん。つまんないもん、そんなことしても。「ここでこういうことを言って」とか「ここはこう動いて」と被写体に指示することは、それをやっちゃったら、何よりも撮ってる自分がつまらないから。
橋本:そういう意味で面白いなと思ったのは、試写会に来た人の誰かの評のなかに、「NEW REPUBLIC」の外人のインタビュアーがふたり取材に来ているじゃないですか。あれもやらせじゃないか、というのがあって。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
編集しながら常に「観客に揺らいでほしい」と思っていた(森)
──自主上映はなかなか難しいとしても、この映画はあらゆる映像学校の教科書にはなりますよね。真贋探しではないとしても、これを観て、何がFAKEか、森さんが仕掛けようとしていることを読み取ることが、観る側が実験台のモルモットかリトマス試験紙になり、「お前、これ観てどう思うんだ」とリテラシーをつきつけられているように思います。ちょっとした簡単な観方をしてしまうと、森さんにあざ笑われそうで。
橋本:森さんは、あざ笑うとかそんな人じゃないよね、ずっと昔から知っているけど、こんなに優しい人なんだと一緒に仕事をして、初めてわかった。
森:編集しながら、「揺らいでほしい」というのは常に、編集担当の鈴尾啓太ともいつも話していました。右行くと思わせたら、今度は左に思わせる、ということはやっています。
──そうした「人をマニピュレートする」手法が、森さんが言う「嘘をつく」ということなんでしょうか。
森:マニピュレートじゃなくて、実際に人は右もあれば左もあるわけだから、映画でも右を見せたら左を見せるよ、ということです。
橋本:ドキュメンタリーって取材しているプロセスが大切なので、取材のときに、右だと思ったり左だと思ったり、揺れがあったはずなので、作為ではなく、その揺れの感覚は絶対に活かすべきです。
──それは取材中にあったのですか?
森:たっぷりありました。さっきも言ったように、僕はテレビは大事なメディアだと思っているけれど、今のテレビに文句があるとしたら、すべてを四捨五入して整理しすぎてつまらなくしてしまうところ。
──揺らぎの部分を許容できないんですね。
橋本:揺らいでいる、というのは、別に観客に「揺らいでください」と作為的に作っているのではなくて、もっと素直に言うと、1年半にわたり取材しているなかで、撮っている方もずっと揺らいでいた。決して一直線で取材したのではないので。その揺らぎ通りに作っているわけではないけれど、それに近い感覚を109分に、その1年半の揺らぎを押し込めて作りたかった。
──それは作為ではなく、森さんが1年半で撮っている間に感じたことをもう一回編集で再現したということですか?
橋本:その編集方法は別にしてそうです。やっぱり揺らいだ感覚は、取材者は全員持ったので。
──多くの作品は、編集する時点で、制作過程で取材者が揺らいでいても、監督は撮り終わってそこでは「あの揺らぎはこっちだったんだ」と、ひとつの方向を見て編集すると思うんです。
橋本:もしかしたら、まだ揺らいでいるのかもしれません。
森:まぁ、それもあるけれど、プレスにも書いたけれど、僕はそうした二極化が嫌いです。黒か白か、右か左か、その間が僕は大好きだし、そこにこそ本質があると思っているので。揺らぐことは、その間を出すことだから、間をどうやって見せるかで、確かに間だけ見せてしまうととても曖昧です。でも右と左のあいだの揺らぎを見せれば、その間が想像できるし……しいて理論づければそういうことになります。
──先日試写で観たものと公開するバージョンは異なるとのことですが、映画のなかでフジテレビの方が2回出てきますが、最初に出てくる番組には、佐村河内さんがいちど出演しているのですよね。
橋本:そうです。そのことを公開バージョンでは、明示しています。そのほか足りないテロップがかなりあることに気がついたので、2、3ヵ所補足しています。
──そこで、テレビに出てくる佐村河内さんを入れなかったのはなぜですか?
橋本:最初は、報道番組の交渉、取材、放送とすべて入れてました。でも、最終的にはずしたのは、段取りくさいからだと思うけれど、違う?
森:それもあるけれど、尺という理由もある。3時間だったら入れたと思う。実際に彼らが取材に来たときには、山崎さんに撮影に入ってもらって、オンエアまで全部撮ったんです。フジの報道はとても誠実に取材した。それはそれで残そうと思ったんだけれど、誠実に、というのは逆に言えば平坦になってしまうわけで。それもあって、最初は入っていましたけれど、最終的に切りました。編集は優先順位の決定です。べつにそこに他意はないです。
橋本:その番組は佐村河内さんが記者会見に出席して以来、始めて出演した番組なので。
──映画では佐村河内さんが出演した番組はカットして、出演していない番組を使用している。そのフジテレビの大晦日の番組は、あんなふうに新垣さんをバラエティで使ったように、結局面白おかしくテレビはネタとして、どっちに転んでもやってたなと。そこは揺らぎでなはく、観ているほとんどの人が分かるシーンだと思いました。森さんは、テレビを観ている佐村河内さんに、「テレビってこんなもの」みたいなことをおっしゃっていたけれど、何とおっしゃっていたんでしたっけ。
橋本:これはテレビの本質を言い当てているんですけれど、「テレビは目の前にあるものがいちばんなんだよね」って。
森:彼は「自分が復讐されている」と、さかんに言うわけです。それは違う。悪意ではない。メディアはそれほど暇じゃない。だから「目の前にあるものをどうやって面白くするかしか考えていないから、あなたがもし出ていればそれなりのものを作ったかもしれないけれど、今回出なかったからこういうことになったんだよ」と、言いました。
橋本:全てのテレビがそうじゃないですけれど、私もテレビの人間なのでそうした思考回路はあります。
──テレビマンも、もし佐村河内さんが出ていれば、あそこまでバラエティで馬鹿にすることはしなかったかもしれない。
森:目の前の事態にだけ反応するから、それによって誰かが傷ついたり追いつめられたりすることに想像力が働かなくなる。でもこれって要するに、ホロコーストに加担したアイヒマンと同じです。アイヒマン自体に悪意はないけれど、結果として良かれと思って組織のなかで任務をこなしているうちに、多くのユダヤ人を殺戮する行為に加担してしまっているわけで。凡庸な悪ですね。彼らもそうした自覚はぜんぜんない。僕も、あそこでは彼らはそこで誠心誠意口説いていると思います。でも結果として、彼を傷つけていることをまったく意識に置かなくなってしまう。そしてこれは、出演する芸人や、さらにそのテレビ番組を見ながら大笑いしている人たちも同様です。
映画『FAKE』より ©2016「Fake」製作委員会
やっぱりドキュメンタリーは相互作用だと思っている(森)
──フジテレビのスタッフは、当然出演をOKしているのですか?
橋本:どの取材も、佐村河内さんの弁護士さんが「密着して記録します、それでもいいですか」と聞いて、納得したうえで取材に来ています。マンガの「淋しいのはアンタだけじゃない」では、そのあたりの取材にいたるまでの経緯も、大変詳しく描かれています。
──報道番組ではないので、公平性を『FAKE』に求めてもまったく意味がないと思うけれど、もし最初に交渉した別のフジの番組に佐村河内さんが出ていたなら、それを5秒でも見せてくれると、出た番組と出てない番組があって、出なかったからこうされたんだ、とより彼らの仕事が分かると思いました。フジテレビに対してはフェアではないなと。映画を観る人はテレビのいいかげんなところだけが強く印象に残る。
森:対比してしまったら、どうしようもないスタッフとの文脈が強調される。そうではなくて、彼らはメディアとしては普遍的な存在です。誰もがアイヒマンになりうる。僕自身の姿でもあるわけです。
──映画のなかで森さんが分からなくなるのは、けっこうテレビのバラエティ的な画を撮りたがる発言、例えば佐村河内さんが「愛してる」と言ったときに「誰をですか?」と念押しして、奥さんの名前をあえて言わせようとしたり。ここから先は言わないで下さい、という後半の一歩手前で、「音楽やりませんか、湧き上がっていますよね、出口を欲しがっていますよね」とけしかけているのは、カットしようと思えば編集でいくらでもカットできたのに、あえて入れますよね。
森:今浅井さんはバラエティ的だと言ったけれど、ドキュメンタリー的だとあれはカットするの?
──カットすると思います。
橋本:私はドキュメンタリーの人間だけれど、あのやりとりはたぶんまるごと入れることに意味があると思っています。
──もし僕が監督するとしたら、そこまで突っ込んで言わないかもしれないです。
森:なぜ残したのかと聞かれても返答に困るけれど、しいていえば、僕はやっぱりドキュメンタリーは相互作用だと思っているから。こちらを切り離して被写体だけで成立するわけじゃないですか。常にこちらの意図もあるし、誘導もあるし、その誘導も裏目に出て誘導されることもある。全部ひっくるめて僕はドキュメンタリーを面白いと思っている。だから、バラエティかドキュメンタリーか、というよりも、面白いから入れたということに尽きてしまう。
──それは編集するとき、撮るときに、このお客さんのことを常に相当意識しているということですか。
森:もちろん意識するけれど、どっちかといえば、過剰に意識はしてないかな。
──でもこの編集でどう観客が心理的に捉えるか、とか、どこで音楽を入れれば感情を昂ぶらせられるか、というテクニックはあるじゃないですか。
森:それはもちろん全カット考えています。
──ということは、観客が揺れをどっちにとるかを意識しているということですよね。
森:今の質問に答えるなら、あそこで僕の声を残したのは、最初から残すことが前提だったから。切るという発想はまったくなかったので、ここに森の声を残す残さないかなどの煩悶はまったくなかった。僕のなかではあって当たり前だった。
橋本:浅井さんが切る、といってなるほどと思いました。
森:テレビだったら切るかもね。
橋本:切らないよ。
森:人によって違うけれど、NHKだったら切るかな。
橋本:いやそうでもないよ。正解はないので。
森:そうですね。正解はない。映画にもいろんな人がいるけれど、でも作法として、テレビは主観を嫌うから。だからあまりディレクターの主観的なことをあまり出してほしくない、というのは映画に比べれば多いんじゃないかな。
──今回は今までの作品とくらべて、カメラの主観ではなく、森さんは出演者ですよね。
森:僕は毎回そうですよ。だからさっき言ったように、作る側の意図や作為をないことにしたら、僕のドキュメンタリーは成立しないから。
──今回カメラは何パーセントくらいが山崎さんなんですか?
森:実はけっこうバッサリ山崎さんのパートを落としているんです。
──今までは森さんのカメラはPOV、主観に見える。でも今回は、森さんが出ているところは山崎さんが撮っているから、観る側は森さんが出演していると感じる。
森:そんなに大きなことじゃないし、『A2』も僕が施設のなかで食べてるシーンとか、安岡卓治が撮ったりしているよ。だから、それは何らかの論があって使い分けているわけではないです。必要とあれば出るし、必要なかったら消すし。
結末を知っていたら面白くない、という単純な映画ではない(橋本)
──最後の12分間については、マナーとして聞かないけれど、「誰にも言わないでください、衝撃のラスト12分間」というコピーは、宣伝としてうまいと思いました。
森:東風がいろんなキャッチコピーのなかで選んだので、僕も、ミステリー映画みたいで、その手があるね、という感じでした。
橋本:私はそろそろ、知られてもいいと思っているんです。結末を知っていたら面白くない、という単純な映画ではないと思うので。
森:でも知らずに観たほうがぜったいにいいでしょう。「え、こうなっちゃうの」って観たほうがぜったいに面白い。
──インタビューの最後として考えていた質問、いちおう言いますね。森さんの映画を真似て、佐村河内さんを騙していないですよね?
森:うーん、ノーコメント。
橋本:……。
森:「僕も橋本も沈黙していた」と書いてください。というか、これまでドキュメンタリーを撮りながら、被写体を騙さなかったことなんてないですよ。それこそ小さな嘘はいっぱいついているし、当たり前じゃないですか。
橋本:嘘つきなんだ……。
木下:嘘という表現は誤解を与えてしまうかもしれないですね。
森:嘘つきでいいよ。今も彼とは普通に会いますよ。
橋本:佐村河内さんは電話ができないのでメールの人なんですよ。電話だと奥さんに電話して、奥さんがしゃべって彼に伝えるから、2倍時間がかかるんです。
森:今日実は、佐村河内さんからwebDICEの取材依頼はお断りしたい、とメールが来ていたんです。だからほっといても浅井さんは取材できなかった。でも僕は、なぜよりによって浅井が、というのがあったので、最初にムカッときたけど。
橋本:佐村河内さんは映画のためにいろいろ協力したいけれど、できれば受けたくない、沈黙したい、という言い方でした。
──僕も森さんと同じですよ、好奇心だもの。
森:でもパブリックに載せるなら、断ります。
──はい、なので森さんとの関係をとると言いました。
森:僕は最初に彼に言ったんです、「あなたの名誉回復のための映画を作る気はさらさらない」と。「僕は映画のためにあなたを利用します」って。彼はしばらく考えていたけれど、でもそれでもいいと。最初は彼は嫌がったんです。何度も口説いているうちに、「分かった」と言ってくれたけれど、そのときに僕が言ったのは、この言葉です。
「やらせ」があるないという浅いレベルで議論するのは貧しい(森)
──町山さんの「やらせ」という解説は否定するのですね。
橋本:「やらせ」ってテレビではもう数十年にわたり、何度となく議論されてきました。「やらせ」の定義とか、ドキュメンタリーにおける「やらせ」ってなんなのとか。この話を始めたら、『朝まで生テレビ』ですまないですよ。「やらせ」かどうかという、きわめて雑な質問には答えづらいですね。
森:なにかに書いたけれど、ドキュメンタリーってただ漫然とカメラを回して撮れるわけないじゃないですか。
──でもそういう意味では、この映画はラストだけではなく、はじめから「やらせ」だよね。
森:化学の実験だと思うんです。フラスコのなかに被写体を入れて、火で炙ったり、振ったり、冷却したり、時には触媒を入れたり、場合によっては撮影する側がカメラを持って一緒にフラスコのなかに入ったり。逆に刺激しているつもりが刺激されたり、それを撮るのがドキュメンタリーだと思っています。それが演出です。漫然と撮るだけで作品になるはずがない。こうした作為を広義でいったら「やらせ」と呼びたい人がいるかもしれないけれど、だったら「やらせ」でいいです。でも当然ながら挑発したり誘導したり、場合によってマウントをとったりとられたり、そうした過程があるから、作品になるわけで。だから、それを「やらせ」があるないというとても浅いレベルで議論するというのは非常に貧しいし、つまらない。
──戦争のドキュメンタリーではエンベッド(軍隊に同行しながら取材すること)して撮影する、それは挑発しようもなくてとりあえず起こったことを撮るしかない。
森:それは延々と戦場シーンだけの場合でしょう。例えば『アルマジロ』もそうだけど、戦闘後に基地に戻った兵士たちがトランプやったりネットのエロサイトを見て大騒ぎしたり、当然ながらいろんな要素が雑多にあるわけです。それを撮るのか、あるいは編集で残すのか残さないのか、それは撮る側の主観です。客観性など欠片もない。
──では最後に、森さんのドキュメンタリーを撮りたい、といったら断りますか?
森:僕を?断ります。そんな度胸ないです。
──ありがとうございました。森さん、これ一応全部書き起こしますので、赤を入れてくれませんか。
森:わかったよ、ホントしつこいよな。
浅井さん、ちょっと飲んでいこうか。本当はもっと聞きたいことあるんでしょ。
(2016年4月21日、ドキュメンタリージャパンにて インタビュー:浅井隆)
森達也 プロフィール
1956年、広島県呉市生まれ。立教大学在学中に映画サークルに所属し、自身の8ミリ映画を撮りながら、石井聰亙(現在は岳龍)や黒沢清などの監督作に出演したりもしていた。86年にテレビ番組制作会社に入社、その後にフリーとなるが、当時すでにタブー視されていた小人プロレスを追ったテレビ・ドキュメンタリー作品「ミゼットプロレス伝説 ~小さな巨人たち~」でデビュー。以降、報道系、ドキュメンタリー系の番組を中心に、数々の作品を手がける。95年の地下鉄サリン事件発生後、オウム真理教広報副部長であった荒木浩と他のオウム信者たちを被写体とするテレビ・ドキュメンタリーの撮影を始めるが、所属する制作会社から契約解除を通告される。最終的に作品は、『A』のタイトルで98年に劇場公開され、さらにベルリン国際映画祭など多数の海外映画祭でも上映され世界的に大きな話題となった。99年にはテレビ・ドキュメンタリー「放送禁止歌」を発表。2001年には映画『A2』を公開。06年に放送されたテレビ東京の番組「ドキュメンタリーは嘘をつく」では村上賢司、松江哲明らとともに関わり、メディアリテラシーの重要性を訴えた。11年には東日本大震災後の被災地で撮影された『311』を綿井健陽、松林要樹、安岡卓治と共同監督し、賛否両論を巻き起こした。「放送禁止歌」(光文社/智恵の森文庫)、初の長編小説作品「チャンキ」(新潮社)など著作も多数発表している。
橋本佳子 プロフィール
1981年12月、フリーで活動していたディレクターの河村治彦、広瀬涼二、テレビカメラマンの山崎裕らと制作プロダクション、ドキュメンタリージャパンを設立。1985年より代表を20年間務める。ドキュメンタリー番組を中心に数多くの作品をプロデュース。放送文化基金個人賞、ATP個人特別賞、日本女性放送者懇談会賞受賞。座・高円寺ドキュメンタリー映画祭実行委員。近年は、『ニッポンの嘘 報道写真家 福島菊次郎 90歳』(12/長谷川三郎監督)、『フタバから遠く離れて第1部・第2部』(12・14/舩橋淳監督)、『ひろしま 石内都・遺された者たち』(12/リンダ・ホーグランド監督)、『祭の馬』(13/松林要樹監督)、『戦場ぬ止み』(15/三上智恵監督)、『広河隆一 人間の戦場』(15/長谷川三郎監督)などを手がける。戦後70周年の節目に制作され、監督に是枝裕和、朗読に綾瀬はるかを迎えた『いしぶみ』が2016年7月16日よりポレポレ東中野ほかにて劇場公開。
映画『FAKE』
6月4日(土)より、ユーロスペースにてロードショー
他全国順次公開
監督・撮影:森達也
プロデューサー:橋本佳子
撮影:山崎裕
編集:鈴尾啓太
制作:ドキュメンタリージャパン
製作:「Fake」製作委員会
配給:東風
2016年/HD/16:9/日本/109分
公式サイト:http://www.fakemovie.jp/
『A2 完全版』
ユーロスペースにて上映
6月18日(土)~24日(金)連日21:00~
7月19日(土)~15日(金)連日21:00~
▼映画『FAKE』予告編
[youtube:GTrgVI-mDdA]